ご注意!
・この診療は、検査から治療まですべて健康保険が適用されないため完全に自費診療です。
・自費外来の診療時間は、月・火・金・土の14:00~15:00です。
このようなお悩みはありませんか?

- イライラする、朝起きるのが困難な方
- 体の内部から美容ケアをすることに興味がある方
- 更年期による不定愁訴で困っている方
- なんとなく元気がない、だるい、疲れやすい方
- 人間ドック、検診、その他保険診療による検査で問題がないのに体調がすぐれない方
- 上記以外に、こちらに該当する方
「そういう体質だろうから仕方ない」、「ちょっとした体調不良だろう」と片づけていた症状が、実は栄養不足が原因であることも少なくありません。
当院では、対症療法だけでなく、根本的に体質を改善できるようサポートします。
当院の栄養ドックを受けるメリット
保険診療では調べない項目をカバー
保険診療の検査がすべてを網羅しているわけではありません。一般的に「原因不明」とは、保険がきく検査で原因を特定できないことを言うことが多く、栄養ドックの検査で原因が判明することがあります。「原因不明」のまま生活することは精神衛生上もよくありません。
バイオメディカル検査のメニューが充実している
メイン検査である「栄養解析検査」ではカバーできない領域(有害物質や腸内細菌、遺伝子など)も対応しています。
体に負担が少ない検査
採血、採尿、手に光を当てる、息を吐く、といったように、体への負担がほとんどありません。
米国の最新検査も
国内で検査するものだけでなく、機能性医学の先進国アメリカに検体を送って検査するものもあります。
栄養ドックのバイオメディカル検査メニュー
栄養ドックの検査は、メイン検査である「栄養解析検査」と、症状に応じて選ぶ各種オプション検査で構成されています。栄養療法では、通常、「栄養解析検査」を受けていただくことが多いですが、症状などに応じてオプション検査をお勧めする場合があります。また、ご希望の検査を指定していただくこともできます。
| 栄養ドック バイオメディカル検査メニュー |
||
| 概要 | 料金(税込み) | |
| 【メイン検査】 | ||
| 栄養解析検査 | 栄養に関する70項目を調べる血液・尿検査。 | 22,000円(説明料込み) |
| 【オプション検査】 | ||
| オリゴスキャン | 有害金属、ミネラルの検査(光を手に当てる)。 | 16,500円(説明料込み) |
| 有機酸 | 76項目の代謝物を測定する尿検査。代謝、腸の状態、中枢神経機能、エネルギー産生能力、胃腸の菌レベル、栄養状態などがわかる。 | 為替レートによる(説明料込み) |
| 25-OH ビタミンD | ビタミンDの血液検査。主にビタミンDサプリメントの効果を確認するのに用いる。 | 3,300円 |
| 遅延型フードアレルギー | 遅延型食物アレルギーの血液検査。 | 219項目:55,000円 120項目:38,800円 (説明料込み) |
| 遅延型フードアレルギー+リーキーガット | 遅延型食物アレルギー176項目とリーキーガットの血液検査。 | 104,500円(説明料込み) |
| リーキーガット | リーキーガット(腸管漏出)症候群の血液検査。 | 28,500円(説明料込み) |
| SIBO呼気検査 | 小腸内細菌増殖症の呼気検査。 | 42,500円(説明料込み) |
| Trio Smart | SIBO呼気検査。従来の検査では水素とメタンの2種類のガスを測定するが、この検査ではさらに硫化水素も加え3種類のガスを測定する。 | 為替レートによる (おおむね110,000円~、説明料込み) |
| IBS Smart | 感染後過敏性腸症候群かどうかを、抗体の有無を測定して調べる血液検査。 | 為替レートによる (おおむね60,000円~、説明料込み) |
| GI-MAP(総合便PCR検査) | 病原菌、常在菌、日和見菌、原虫、真菌、ウイルスなどを測定して消化器の健康状態を総合的に調べる便検査。特に、過敏性腸症候群、SIBO、リーキーガットにお勧め。 | 為替レートによる(説明料込み) |
| GI-MAP+ゾヌリン | GI-MAPにオプションのゾヌリンを追加。ゾヌリンを測定することでリーキーガットの有無がわかる。 | 為替レートによる(説明料込み) |
| GI-MAPのオプション検査「グルテンペプチド」 | GI-MAPに追加できるオプション。グルテンを避ける食事に移行した後にその効果を確認するのに用いる。 | 為替レートによる(説明料込み) |
| GI-MAPのオプション検査「総合抗生剤耐性」 | 抗生剤の耐性の有無を確認する検査。 | 為替レートによる(説明料込み) |
| GI-MAPのオプション検査「StoolOMX」 | 便中の25種類の胆汁酸と9種類の短鎖脂肪酸の量を調べる検査。 | $200(為替レートによる) |
| 腸内細菌(腸内フローラ) | 多様性、短鎖脂肪酸、腸管免疫、口腔常在菌の4つの指標に基づいて腸内フローラの状態を調べる便検査。 | 初回:22,000円 2回目以降:16,500円 (説明料込み) |
| 副腎ストレス | 副腎のストレス度合いを調べる唾液検査。特に慢性疲労やうつ症状に。 | 46,000円(説明料込み) |
| コルチゾール日内変動 | コルチゾール濃度の日内変動を調べる唾液検査。 | 23,000円(説明料込み) |
| コルチゾールリズム | コルチゾールの日内変動とDHEAを調べる唾液検査。 | 30,000円(説明料込み) |
| トリマーキュリー(水銀) | 世界特許を有する水銀検査で、毛髪、尿、血液の3つの経路で水銀の蓄積量を正確に調べることができる。 | 55,000円(説明料込み) |
| 体内カビ検査 | 体内のカビを調べる尿検査。 | 為替レートによる(説明料込み) |
| 生活環境化学物質検査(TOXDetect) | 日常生活で触れることが多い19種類の化学物質にどれだけ体が曝露しているかを調べる尿検査。 | $330 (その時期の為替レートによる、説明料込み) |
| Dダイマー | 1,200円 | |
| FreeStyleリブレ | 1日の血糖値の変動を調べる検査。 | |
| MCIスクリーニング検査 | 軽度認知症のリスクを調べる検査。 | 24,200円(説明料込み) |
| ApoE遺伝子検査 | 認知症のリスクを調べる検査。 | 22,000円(説明料込み) |
| ホルモン年齢 | 成長ホルモン(IGF-Ⅰ、DHEA-s)とストレスに関係するホルモン(コルチゾール)を調べる血液検査。 | 13,200円(説明料込み) |
| Lox-IndexⓇ | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを調べる血液検査。 | 18,700円(説明料込み) |
| サインポスト「生活習慣予防プログラム」 | 16の体質分野について357種類の遺伝子を調べる検査。 | 22,000円(説明料込み) |
| サインポスト「肌老化予防プログラム」 | 70種類の遺伝子を解析し、12項目の肌老化に関するリスクを調べる。 | 49,500円(説明料込み) |
| サインポスト「がん遺伝子」検査 | 100種類以上の遺伝子を測定し、男性12項目、女性14項目のがんのリスクを調べる検査。 | 49,500円(説明料込み) |
| マイクロアレイ | 金沢大学が開発した遺伝子レベルでがんの存在を突き止める高感度遺伝子検査。 | 110,000円(説明料込み) |
栄養解析検査について
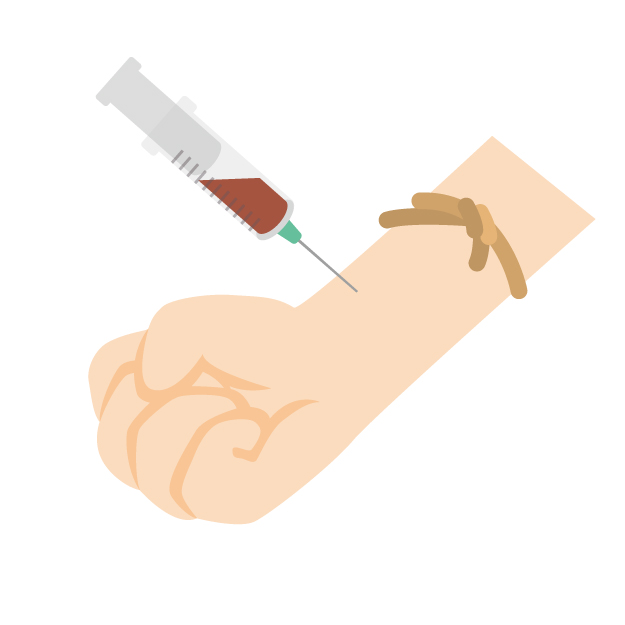 原因不明の体調不良は、実は栄養不足が原因となっていることもあります。必要な栄養をしっかりと補給することで、症状だけでなく全身の状態やQOL(生活の質)の改善に効果があるとされています。私たちの身体は日々の何気ない食事によって作られています。栄養解析ドッグでは、医療用サプリメント、適切な食事指導、点滴療法などを行って、不足している栄養素を補給し、根本的に体質を変えられるようサポートいたします。
原因不明の体調不良は、実は栄養不足が原因となっていることもあります。必要な栄養をしっかりと補給することで、症状だけでなく全身の状態やQOL(生活の質)の改善に効果があるとされています。私たちの身体は日々の何気ない食事によって作られています。栄養解析ドッグでは、医療用サプリメント、適切な食事指導、点滴療法などを行って、不足している栄養素を補給し、根本的に体質を変えられるようサポートいたします。
オーソモレキュラー栄養療法の検査である「栄養解析検査」では、70にも及ぶ項目について検査を行います。通常の検診などでは「異常なし」とされていても、オーソモレキュラー療法のアプローチでは「異常なしとはいえない」場合も多くあります。たとえば、肝機能の指標として知られる「AST」、「ALT」という項目があります。数値が正常値をオーバーしていれば「異常あり」、正常値よりも低ければ「異常なし」とされるのが一般的な検査です。
一方、オーソモレキュラー栄養療法ではこれらの数値が低くても、両値の差が2を超えている場合「ビタミンB不足」であるとみなします(AST:20、ALT:16など)。「尿酸値」の場合、正常値を超えていなくても、この値が低過ぎると「抗酸化力の低下」を疑います。
このように、オーソモレキュラー栄養療法のアプローチにより、通常の検診や検査では「異常なし」とされていても必ずしも「異常なし」ではないことがわかり、不調の原因が明らかになるということもあります。
この検査の結果、たとえばカルシウムが不足している場合、「じゃあ、カルシウムのサプリメントを飲めばいいのね」ということになるかと思いますが、実際はそう単純でないことが多いです。これにリンの値が高い場合、この過剰なリンによってカルシウムが阻害されるため、リンの摂取を抑えるような食事療法も並行してご提案することになります。つまり、検査結果の1項目だけに注目するのではなく、横断的な視点でもみて総合的に判断しながら栄養療法を行わないと、ずっとサプリメントを続けているのに一向に良くならないといったことが起こります。せっかく検査をしても、その結果を100%活用できず体調が良くならないため、ドクターショッピングや別の検査を重ねてしまうということも珍しくありません。
このように、体の構造と栄養についてどの程度医師が熟知しているかが、栄養療法ではきわめて重要であるといえます。
このようにこの検査では、70にも及ぶ項目にこのようなアプローチをとりながら不調の原因を探っていきます。
オーソモレキュラー栄養療法と一般的な検査の解釈の違い
| 検査項目 | 一般的な検査での解釈 | オーソモレキュラー栄養療法での解釈 |
|---|---|---|
| 総タンパク | 栄養状態、肝・腎機能 | 全身状態、タンパク代謝、酸化ストレス |
| アルブミン | 栄養状態、肝機能 | 全身状態、タンパク代謝 |
| AST(GOT) | 肝機能 | 全身状態、タンパク代謝、ビタミンB6不足、酸化ストレス |
| ALT(GPT) | 肝機能 | 全身状態、タンパク代謝、ビタミンB6不足、酸化ストレス |
| ALP | 肝機能 | 亜鉛不足 |
| LDH | 貧血、炎症、骨疾患 | 全身状態、タンパク代謝、ナイアシン不足 |
| γ-GTP | 肝機能、胆道系 | 全身状態、タンパク代謝、酸化ストレス |
| コリンエステラーゼ | 肝臓疾患 | 全身状態、タンパク代謝、脂質代謝 |
| 総コレステロール | 高コレステロール血症 | 全身状態、タンパク代謝、脂質代謝、糖代謝 |
| LDLコレステロール | 冠動脈疾患リスク | 全身状態、タンパク代謝、脂質代謝、糖代謝 |
| HDLコレステロール | 動脈硬化リスク | 全身状態、タンパク代謝、脂質代謝 |
| 中性脂肪 | 肥満状態 | 全身状態、タンパク代謝、脂質代謝、糖代謝、酸化ストレス |
| クレアチニン | 腎機能 | 全身状態、タンパク代謝、筋力低下 |
| ヘモグロビン | 貧血 | 全身状態、タンパク代謝、ビタミンB6不足、鉄不足 |
| ヘマトクリット | 貧血 | 全身状態、タンパク代謝、鉄不足 |
| 血清鉄 | 貧血 | 全身状態、タンパク代謝、鉄不足、酸化ストレス |
| フェリチン | 悪性腫瘍 | 全身状態、タンパク代謝、鉄不足 |
※上記の検査項目と解釈の内容はほんの一例です。
実際の栄養解析検査では、上記に加え計70にも及ぶ項目を検査します。また、解釈の内容も一例であり、実際には、個々の項目を独立してみるだけでなく、関連し合う複数の項目を総合的にみて判断するものもあります。このように、検査項目を個別にみたり複合的・総合的にみたりして栄養学的な判断をするのがオーソモレキュラー栄養療法です。
単に結果の数値が正常範囲にあるかどうかに留まらず、オーソモレキュラー栄養療法的な数値の見方に医師がどの程度精通しているかがこの検査の要であるともいえます。
検査概要
血液検査を行って細胞を分子レベルで分析することで、全身の状態をチェックします。検査結果に応じて、必要となる栄養素を補給することで、細胞の修復・合成を促して体調不良を改善することで、全身の状態も正常に近づけていきます。また、必要な栄養素を補うことで身体の自然治癒力を促進し、病気や不定愁訴の予防・改善を後押しします。
自分に必要な栄養素を知りたい、自分の力で健康管理をしていきたい、薬を飲まなくても済むような丈夫な身体づくりをしたいという方は、予防医療としてぜひ一度ご検討ください。
検査の流れ
1カウンセリング
専門医がお悩みをしっかりと伺います。
2問診票に記入していただき、血液検査をして栄養解析検査を行います
一般的な血液検査では行わないものも含めて70項目以上を検査します。
チェックシートの記入が終わりましたら、日々の食事メニュー、生活習慣、お困りの症状などについてお聞きします。
血液検査による栄養解析は些細な疾患の兆候も発見可能
血液検査で70項目以上を検査することで、自覚していないような体内の栄養状態を把握することに繋がります。例えば、健康診断では特に異常が見つからなかった方でも、隠れ高血圧、隠れ貧血などの数値異常が発見されることも少なくありません。
また、一般的な健康診断では基準値の範囲内として考えられるものも、当院で実施する栄養解析ドッグでは些細な兆候も見逃さずにチェックしていきます。
3(約2週間後)検査結果をご説明し、治療方針を決定します
4(3〜4ヵ月後)ご希望に添って再検査を数ヵ月後に行い、体の状態を再確認します
血液検査やカウンセリングを改めて実施し、栄養状態を確認します。
栄養ドックの所要時間
- 栄養解析検査(血液検査):約5分
- 医師による栄養解析カウンセリング:約30分
よくある質問
栄養解析検査ではなく、オプション検査だけでも受けられますか?
はい、受けていただけます。電話での予約時にその検査名をお知らせください。
初診から検査を受けられますか?
当日や前日から食事制限が必要な検査があります。これが守られていれば基本的には可能です。
初診の予約を電話でおとりになる際、当日に検査を受けたい旨をお知らせください。
検査の料金には何が含まれますか?
検査料と結果の説明料が含まれています。
他院で受けた検査の結果を持参した方がいいですか?
あれば持参してください。今後の治療の参考とするために拝見します。ただし、検査結果に関する説明や解釈が必要な場合、別途11,000円のご負担をお願いします。
栄養ドックの費用
| 診療メニュー | 料金(税込み) |
|---|---|
|
カウンセリング料 |
初診(25分):11,000円 再診(20分):8,800円 ※初診・再診とも、時間の延長は行っていません。 |
| 栄養解析検査 (初回カウンセリング料(15分)、簡易レポート、結果説明(30分)を含む) |
22,000円 |
| 医薬品・サプリメント | 4,000円~16,000円 |
※詳細レポートを希望される場合、別途6,600円が必要です。
※完全予約制です。必ずお電話で予約をおとりください。
※自費診療枠:月・火・金・土の14:00~15:00(祝日を除く)
栄養ドックのリスクと注意事項
| リスク・副作用について |
|
|---|---|
| 通院ペース | 3ヵ月おきの血液検査、カウンセリング、栄養解析レポートの作成を行ったうえで、栄養療法を1年間は続けていくことがよいとされています。 |
| 備考 | 正確な検査結果を担保するために、最低でも検査の8時間前には食事を済ませておくようお願いします。採血しにくくなるため、水、白湯、お茶(糖分を含まないもの)は飲んでください。コーヒー、たばこ、アルコールは控えてください。女性の場合、生理中は採血できません。 |
オリゴスキャンについて
 体内の有害金属やミネラルは、蓄積や過不足が少量でも私たちの健康に影響を与えることがあります。
体内の有害金属やミネラルは、蓄積や過不足が少量でも私たちの健康に影響を与えることがあります。
「なんとなく体調不良を感じるけど、病院では原因がわからなかった」、「病院で処方された薬を飲んでも症状が改善されない」といった方は、有害金属の蓄積やミネラルの過不足が原因となって体調不良を起こしている可能性があります。また、精神的な不調にも影響を及ぼすため、体内の蓄積状態を一度確認されることをお勧めします。
OligoScan/ オリゴスキャンは、手のひらに光を照射して、数分程度で体内の有害金属14元素、必須ミネラル20元素の蓄積状態を確認することができる検査器です。この検査の最も優れているのは、血液や尿、毛髪、爪などではなく、「組織」に存在(蓄積)している「現在の」ミネラルと有害金属を測定できるという点です。
これはどういったことなのかというと、たとえば、あるオフィス街にいくつか建物があるとします。それらの建物にどういった人たちが何人働いているのかを調べるとします。30代の女性が何人いるのかを調査する場合、実際に建物の中に入って調べる方法と、建物の前を通る道にそういった人が何人歩いているのかを調べる方法があります。道を歩いている人を見れば、建物の中のおおよその人数を予想できますが、実際に建物の中まで入って調べるほど正確ではありません。つまり、道(血管)を見て調べる方法が血液検査です。そして実際に建物(組織)の中に入って正確に調べるのがオリゴスキャンです。
この「正確」に測定できる、というの大きなポイントなのです。というのも、人間の体はホメオスタシスという機能によってミネラルのバランスが厳密にコントロールされているのですが、この厳密さゆえに少しでもバランスが崩れると、体に悪い影響が出はじめます。そして困ったことに、血液検査ではこの小さなバランスの崩れが明らかになりにくいのです。ちなみに、組織に存在(蓄積)しているミネラルや有害金属を調べるには、実際にメスや針で組織を採取する必要があります。しかしこれでは体への負担が大きく、検査を受けようと思う人はそういないでしょう。
一方、オリゴスキャンは、光を手のひらに当て、その光の吸収、透過、反射の違いを見て解析しているため体への負担が全くありません。また、尿で検査する方法の場合、むしろそのミネラルや有害金属を体内から排除しようとする体の排出能力を評価するのに有用であり、毛髪による検査に至っては「現在」の状態ではなく、数週間から数カ月前のことしかわかりません。このため、『組織』に存在(蓄積)している量をオリゴスキャンで測定しないと、なぜ体に不調が起きているのかを正確に調べることができないのです。ご自身のお身体の状態を適切に把握し、健やかな生活を送るためにぜひ一度検査をご検討ください。
オリゴスキャンで測定できるミネラルと有害金属
| ミネラル | 説明 |
|---|---|
| カルシウム | 主に骨にみられ、神経伝達、筋肉の収縮、血液の凝固作用、組織への酸素供給の役割があります。 不足すると「イライラ」、「情緒不安定」、「骨・歯が弱る」といった症状が出やすくなります。 |
| マグネシウム | あらゆる細胞にみられ、特に骨に多く含まれます。骨の構造維持や、正常な神経・筋肉系の活動をサポートするほか、300以上の酵素反応に関与しています。 不足すると「集中できない」、「筋力低下」、「肌あれ」といった症状が出やすくなります。 |
| リン | cいても重要な役割を果たしています。 リンはあらゆる細胞に欠かせない必須成分です。不足すると「倦怠感」、「疲労感」、「筋力低下」といった症状が出やすくなります。 |
| ケイ素 | 骨、毛髪、爪、軟骨、皮膚の成分であり、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸の生合成に重要な役割を果たしています。 不足すると「爪割れ」、「脱毛」、「皮膚のたるみ」、「血管がもろくなる」といった症状が出やすくなります。 |
| ナトリウム | 体の水分バランス、筋肉・神経の機能維持に必要です。不足すると「倦怠感」、「めまい」、「吐き気」、「低血圧」といった症状が出やすくなります。 |
| カリウム | ナトリウムと連携して体の酸塩基バランスを維持し、細胞の活動をサポートします。 特に、神経伝達や筋肉の収縮に必要不可欠です。不足すると「無気力」、「不安感」、「呼吸障害」といった症状が出やすくなります。 |
| 銅 | 多くの酵素に必要不可欠で、骨、軟骨、鉄の代謝維持に使われるほか、免疫システムを刺激します。 不足すると「食欲不振」、「うつ」、「免疫力低下」といった症状が出やすくなります。 |
| 亜鉛 | 体内で起こる200以上の酵素反応の補因子です。成長、免疫、神経機能に関与しており、多くのホルモンの構造にも関与しています。 不足すると「疲れやすい」、「免疫力低下」、「肌あれ」、「味覚障害」といった症状が出やすくなります。 |
| 鉄 | ヘモグロビンやミオグロビン、その他多くの酵素の形成で基本的な役割を果たしています。 不足すると「倦怠感」、「めまい」、「口内炎」といった症状が出やすくなります。 |
| マンガン | 炭水化物の代謝調節、血液の凝固作用、骨格形成、フリーラジカルの除去など、さまざまな酵素の働きに関与しています。 不足すると「運動機能低下」、「肌あれ」、「性機能低下」といった症状が出やすくなります。 |
| クロム | 体内の他の化合物と結合して、グルコース耐性因子を形成します。また、脂質代謝にも関与しています。 不足すると「消化不良」、「代謝不良」、「糖尿病リスクの増加」といった症状が出やすくなります。 |
| バナジウム | 甲状腺機能と骨代謝で重要な役割を果たしています。不足すると「肥満」、「脱毛」、「動脈硬化」といった症状が出やすくなります。 |
| ホウ素 | 性ホルモンの濃度を高めるほか、骨格の維持に重要な役割を果たしています。不足すると「関節症」、「骨量減少」といった症状が出やすくなります。 |
| コバルト | ビタミンB12の成分です。赤血球の生成や神経の機能維持に寄与しています。 不足すると「食欲不振」、「集中力低下」、「悪性貧血」といった症状が出やすくなります。 |
| モリブデン | タンパク質の消化で生じる生成物を除去するのに必要です。不足すると「頭痛」、「夜盲症」、「居眠り」といった症状が出やすくなります。 |
| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンの必須成分です。体温調節、基礎代謝、生殖、成長、神経の活動などで重要な役割を果たしています。 不足すると「肥満」、「脱毛」、「肌あれ」、「精神発達の遅れ」といった症状が出やすくなります。 |
| リチウム | 神経細胞の活動に関与しています。不足すると「頭痛」、「手足のふるえ」、「うつ」といった症状が出やすくなります。 |
| ゲルマニウム | 組織の酸素化に寄与しています。不足すると「疲労」、「食欲不振」といった症状が出やすくなります。 |
| セレン | 体内の過酸化物を消去するのに必要なグルタチオンペルオキシダーゼの生成に寄与しています。 不足すると「免疫力低下」、「成長障害」、「抗酸化力低下」といった症状が出やすくなります。 |
| 硫黄 | 毒素の除去のほか、組織の合成過程にも関与しています。不足すると「皮膚炎」、「肌あれ」、「脱毛」といった症状が出やすくなります。 |
| 有害金属 | 説明 |
|---|---|
| アルミニウム | 特定の神経系の疾患や過敏性腸症候群の原因とされる有害金属です。 体内に蓄積すると「認知機能の低下」といった症状が出やすくなります。 |
| アンチモン | WHOによると、発がん性の可能性あり(グループ2B)に分類される有害金属で、特定の酵素の活性を阻害し、タンパク質や炭水化物の代謝、肝臓でのグリコーゲン産生を妨害します。 体内に蓄積すると「乾燥肌」、「脱毛」といった症状が出やすくなります。 |
| 銀 | 銀ナノ粒子の毒性に関する研究では、同じ結論には至っておらず相反する意見が論じられていますが、生態毒性学的研究に関していえば、水中生物と陸上生物に対する銀ナノ粒子の生物学的影響(死亡、成長抑制、遺伝毒性、生殖毒性)が示されています。 体内に蓄積すると「皮膚変色」、「記憶力の低下」といった症状が出やすくなります。 |
| ヒ素 | 有害な半金属です。長時間さらされると、皮膚疾患、手足の過角化症、色素沈着が生じる可能性があります。 また、発がん性もあります。体内に蓄積すると「酵素の働きが阻害」される可能性があります。 |
| バリウム | バリウム中毒やその化合物によって、消化器系、筋肉、心臓(不整脈)、神経系が影響を受けることがあり、化合物によっては、長期的に曝露されることで呼吸器疾患や高血圧を引き起こすことがあります。 体内に蓄積すると「筋力低下」、「不安感」といった症状が出やすくなります。 |
| ベリリウム | 慢性的にさらされると、肺肉芽腫症を引き起こす可能性があります。また、DNAを改変する可能性があり、発がん性もあります。 体内に蓄積すると「脱力感」、「呼吸困難」といった症状が出やすくなります。 |
| ビスマス | 蓄積量が高くなると、深刻な神経障害が引き起こされることがあります。 体内に蓄積すると「無気力」、「不眠」、「頭痛」といった症状が出やすくなります。 |
| カドミウム | 腎臓、骨、呼吸器系に毒性があります。発がん性もあります。体内に蓄積すると「節々の痛み」、「腎障害」といった症状が出やすくなります。 |
| 水銀 | WHOによって、きわめて危険な有害元素であるとされています。神経系、消化器系、免疫系、肺、腎臓に有害な影響を及ぼすほか、運動機能障害や認知機能障害を引き起こす可能性があります。 体内に蓄積すると「疲労」、「口内炎」、「免疫低下」といった症状が出やすくなります。 |
| ニッケル | ニッケルアレルギーは決して珍しくなく、通常、接触することで皮膚炎が生じます。ニッケル金属は「発がん性の可能性あり」(グループ2B)に分類されており、その無機化合物は「発がん性あり」(グループ1)に分類されています。 体内に蓄積すると「めまい」、「金属アレルギー」といった症状が出やすくなります。 |
| プラチナ | 気道、肺、皮膚に刺激を与える可能性があります。体内に蓄積すると「皮膚炎」、「聴力障害」といった症状が出やすくなります。 |
| 鉛 | WHOによって、深刻な有害金属とされています。脳や中枢神経系に悪影響を及ぼします。 体内に蓄積すると「貧血」、「高血圧」といった症状が出やすくなります。 |
| タリウム | 体内でカリウムと競合する物質で、きわめて毒性が高い金属です。消化器系に問題を起こしたり、神経精神症状を引き起こしたりするほか、神経障害、頻脈、高血圧、脱毛などの原因にもなりえます。 体内に蓄積すると「吐き気」、「頭痛」といった症状が出やすくなります。 |
| トリウム | 放射性の形態でのみ存在できる元素です。放射線について重要な臓器として、肺、骨髄、骨の表面、生殖器などが挙げられます。体内に蓄積すると「肺」、「膵臓障害」といった症状が出やすくなります。 |
検査の方法
検査機器から発せられる光を手のひらの4ヶ所に当てて確認します。検査時間は3分程度で済み、読み取ったデータを開発元のルクセンブルクにウェブ経由で送信して解析してもらいます。後日来院していただき、結果の内容と今後の治療についてご説明します。

オリゴスキャン検査の費用
| 診療メニュー | 料金(税込み) |
|---|---|
| オリゴスキャン検査(検査結果説明) | 16,500円 |
※初診料が必要な医療機関が多いなか、当院では初診料はいただいておりません。
※完全予約制です。
※食事制限等はありません。
※対象年齢は2歳以上です。
GI-MAP便総合検査について
胃・大腸カメラ、各種血液検査を受けても問題がないのに体調がすぐれない(特にお腹に症状がある)方は、腸内で病原体や細菌、ウイルス、寄生虫などが悪さをしているかもしれません。あるいは、細菌叢のバランスが崩れ、悪玉菌が過剰に増殖して、炎症を起こしていたり、水素、メタン、硫化水素が過剰に増えていてガス溜まりや胃酸が逆流しているかもしれません。
GI-MAP(Gastrointestinal Microbial Assay Plus)検査は、精度がきわめて高い定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)技術を用いて、少量の便から腸内細菌叢のDNAを測定する検査です。通常のPCR検査に比べ、便1グラムあたり0.1個の細胞さえも検出できる感度の高い検査です。
この検査では、病原体、ピロリ菌、常在細菌、日和見細菌、過剰増殖細菌、菌類/酵母、ウイルス、寄生虫などの有無とその量がわかるだけでなく、消化、免疫反応、炎症のマーカーを調べることができます。
細菌やウイルスに感染すると、マスト細胞が活性化されヒスタミンが放出されます。そして、このヒスタミンが免疫系を刺激することにより過敏性腸症候群を発症することがあります(感染後過敏性腸症候群:PI-IBS)。米国のデータですが、このPI-IBSは、食中毒を起こした人の9人に1人が発症するとの報告があります。さらに、下痢型の過敏性腸症候群では、6割近くが食中毒によるものといわれています。
これに関連して、特定の食物が腸内にあるときにある有害微生物に感染すると、その後その食物を摂取するとマスト細胞が活性化され、過敏性腸症候群を発症することもあります。
また、過去に感染した病原菌や微生物が完全には排除されておらず、体内に残っている一部が悪さをして腹部症状や全身症状を引き起こしている場合もあります。
GI-MAP検査で特に注目すべきは、8種類の遺伝子のピロリ菌を高感度に検出できるという点です。通常の検査では見逃される場合でも、GI-MAPでは検出されることも多いです。
ピロリ菌は胃酸の分泌を阻害することで知られています。このため、[ピロリ菌感染]⇒[胃酸低下]⇒[除菌力低下]⇒[有害菌が多いまま食物が小腸に]⇒[小腸で細菌が増殖]⇒[SIBO]ということが起こり得ます。
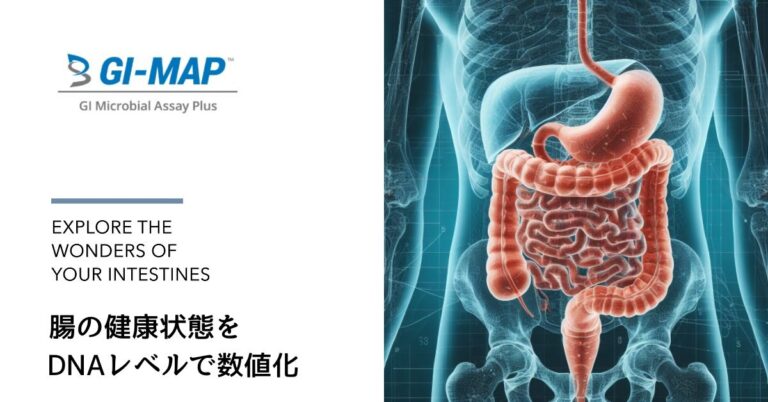
特に、PCR検査でも、この検査は「qPCR」技術を用いていることがポイントです。PCRに「q」が付いているのは、結果値が「定量化」されているという意味です。
たとえば、あなたが血糖の検査を受けたとします。その検査結果が単に「高い」だけだったらどう思いますか?ただ単に「高い」だけでなく「どの程度高いのか?」を知りたくないですか? 「今回の結果は120mg/dLなので基準を少しオーバーしてる」という結果でないと納得できませんよね。 このように、血液検査では結果が具体的な数値で出ることがあたりまえですが、この種の便検査では、あたりまえではありません。「陰性」か「陽性」かしかわからない検査がほとんどなのです。 この点だけでもこの検査が優れていることがわかります。
このほか、40以上の項目を調べることから、腹部の疾患や症状のみならず、糖尿病などの内分泌関係、にきびや乾癬などの皮膚疾患、自閉症などの精神疾患など、多くの疾患に応用できます。 このことから、GI-MAP検査の有用性は非常に高いのですが、便を採取したらアメリカの検査機関に送るため結果が出るまで1~2週間程度要することや、費用が高いといった点をあらかじめ考慮しておく必要があります。
腸内細菌叢のバランスが崩れると
- 腹痛
- 膨満感
- 便秘
- 下痢
- 胃炎、胃腸炎
- 胃食道逆流症
- 過敏性腸症候群
- SIBO(小腸内細菌異常増殖症)
- 潰瘍性大腸炎、クローン病
- 胃がん
- 自己免疫疾患(反応性関節炎、関節リウマチなど)
- アレルギー疾患(喘息、湿疹など)
この検査でわかること
- ディスバイオーシス(腸内細菌叢の異常)
- 病原細菌、酵母、真菌、寄生虫の有無とその量
- 胃腸・消化管の炎症
- 消化吸収機能の健康状態(消化・吸収不良、吸収能力)
- 水素、メタン、硫化水素を産生する菌の過剰増殖(腹部膨満や胃酸逆流を引き起こす、硫化水素が多いおならは臭い、メタンが多いと便秘になりやすい、水素が過剰だと食物の通過速度が早くなり栄養吸収が悪くなるなど)
- ピロリ菌の感染(胃炎、潰瘍、がんやSIBOの原因となり得る)
- 消化管粘膜のバリア機能の状態
- リーキーガット(オプション)
- IBS(過敏性腸症候群)、PI-IBS(感染後過敏性腸症候群)、SIBO
- ウイルス、病原菌への感染
- 膵外分泌機能不全(慢性下痢の原因になり得る)
- 免疫機能の低下
- クローン病、潰瘍性大腸炎のリスク
- 自己免疫疾患(関節リウマチ、クローン病、潰瘍性大腸炎など)のリスク
この検査をお勧めする方
- 胃・大腸内視鏡検査で異常がないのに腹部に症状がある
- 腹部膨満感、ガス溜まりが常態化している
- 原因不明の便秘、下痢が続いている
- SIBO、SIFO、リーキーガット、IBSではないかと感じている
- 皮膚の湿疹、発疹
- 発達障害
- 自己免疫疾患
- 体重がなかなか減らない
- 糖尿病
- 細菌叢の健康状態を知りたい方
- プロバイオティクスサプリメントが必要か知りたい方
検査項目
※横にスクロールできます。
| 項目 | 説明 | マスト※1 | ヒスタミン※2 | LPS※3 | 水素※4 | メタン※5 | 硫化水素※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【病原体】 | |||||||
| カンピロバクター Campylobacter |
食中毒でよくみられる病原菌。わずかな曝露でも感染することがある。激しい腹痛、下痢、発熱、倦怠感などが生じ、数日~数週間に及ぶこともある。 | ||||||
| クロストリジウムディフィシル毒素Aおよび毒素B C.difficile Toxin A/Toxin B |
特に抗菌薬の使用により増殖する。院内感染でよくみられる。毒素を出し、腸管壁に炎症を起こしたり損傷したりする。この値が高いと下痢、腹痛、吐き気、食欲不振、発熱などを起こす。 | ||||||
| 腸管出血性大腸菌 Enterohemorrhagic E. coli |
血便が出る。発熱は軽度。加熱が不十分な肉、生乳、飲料水等から感染する。志賀毒素を出し、溶血性尿毒症症候群を引き起こす場合がある。 | ||||||
| 大腸菌O157 E.coli O157 |
下痢、血便、吐き気のほか溶血性尿毒症症候群などを引き起こす場合がある。 | ||||||
| 腸管侵襲性大腸菌/赤痢菌 Enteroinvasive E. coli/Shigella |
汚染された食品を介して感染し、摂取後12~72時間で下痢、嘔吐、発熱、悪寒、倦怠感、腹部けいれんなどを起こす。侵襲性が高く腸壁を損傷する。重度では、血便や脱水症状を起こし、腎障害を引き起こす可能性がある。 | ||||||
| 毒素原性大腸菌 Enterotoxigenic E. coli LT/ST |
旅行者下痢症の原因菌ともいわれる。汚染された食品を介して感染する。 | ||||||
| 志賀毒素産生大腸菌(志賀毒素1および2) Shiga-like Toxin E. coli stx1/stx2 |
汚染された食品を介して感染する。この値が高いと下痢、腹痛を起こす場合がある。腸壁を損傷する場合がある。 | ||||||
| サルモネラ菌 Salmonella |
最もよくみられる食中毒の原因菌。鶏肉、卵、低温殺菌されていない牛乳など、生または調理不十分な食品や汚染された水を介して感染する。下痢、発熱、胃けいれんなどの症状を引き起こし、通常は感染後12~72 時間以内に現れる。健康な人では通常1週間以内に軽快する。汚染された食品の中にこの細胞がわずか10個あっても症状を引き起こすことがある。免疫力の低下、制酸剤や抗生物質などの使用、汚染された環境や食品源への曝露などにより感染リスクが高まる。 | ||||||
| ビブリオコレラ Vibrio cholerae |
汚染された水中に存在し、重度の下痢、嘔吐、脱水、発熱などの重篤な症状を引き起こす毒素を生成する。 | ||||||
| エルシニアエンテロコリチカ Yersinia enterocolitica |
豚、牛、鳥の腸管にも存在する。汚染された水や加熱不十分な豚肉、その他肉、乳製品などを介して感染する。曝露後4~7日で水様便または血が混じった下痢、腹痛、発熱、嘔吐などが生じる。炎症性腸疾患、特にクローン病と所見が似ている。鉄を好む性質があるため、特に遺伝性ヘモクロマトーシスを有する人は感染に注意する。この菌の尿路感染は、反応性関節炎をはじめとする炎症性疾患に関連している。 | ||||||
| 【寄生性病原体】 | |||||||
| クリプトスポリジウム Cryptosporidium |
人間と動物の両方に感染する。プール、湖、小川などの汚染された水源でよくみられ、誤って水を飲み込んだときに体内に入り込む可能性がある。体内に入ると、消化器系に影響を及ぼし、下痢、腹痛、吐き気、ガス溜まり、膨満感などの症状を引き起こす。健康な人では、通常2~3週間以内に軽快する。 | ||||||
| 赤痢アメーバ Entamoeba histolytica |
汚染された食品を介して感染する寄生虫。衛生状態の悪い地域に旅行したときなどに感染しやすい。感染しても必ず発症するとは限らず、腹痛や軟便など軽度の場合が多い。肝臓に感染したり、肺や脳など、体の他の部位に広がることがあるが、その発生率は低い。 | ||||||
| ジアルジア Giardia |
ジアルジア症と呼ばれる一般的な腸の感染症の原因で、下痢、腹痛、膨満感、倦怠感、嘔吐、体重減少、蕁麻疹、栄養失調、子どもの成長遅延、拒食症、脂肪便などを引き起こす。特に、栄養失調、免疫抑制、嚢胞性線維腺症の人に重大な症状を引き起こすことがある。汚染された食品や、人・動物との直接接触により感染する。嚢胞と呼ばれる硬い殻に包まれており、体外で長期間生存でき、一般的な消毒剤に耐性がある。体内に入ると嚢胞が開き、活動にある寄生虫が放出され、腸壁に付着して増殖する。ジアルジア症の診断にあたり、PCR法は、便中のジアルジア属を便100マイクロリットルあたり寄生虫を10個レベルで検出でき、軽度および無症候性の感染症を識別できるとされている。 | ||||||
| 【ウイルス病原体】 | |||||||
| アデノウイルス40/41 Adenovirus 40/41 |
胃腸炎を引き起こす。乳児や小児の下痢の一般的な原因。大人でも感染する。通常、発熱と水様性の下痢は1~2週間で軽快する。この40/は、無症候性キャリアの便中にも存在する可能性があり、特に治療を要しないこともある。この40/41は、胃腸に関するものだけでなく、気道感染から膀胱感染までさまざまな部位に感染する。重篤な症状になることは少ないが、免疫力が低下している人は注意する。 | ||||||
| ノロウイルスGIおよびGII Norovirus GI/II |
最も一般的な非細菌性胃腸炎の原因とされる。感染者との接触、または汚染された食品の摂取後24~48時間で発症する。症状として、嘔吐、腹痛、下痢、微熱、筋肉痛、倦怠感、頭痛などが挙げられる。安定性、耐熱性、耐寒性に優れ、感染力がきわめて強い。硬い表面では数週間、汚染された布地では最長12日間生存できる。感染すると結腸ではなく、小腸の微絨毛に影響を与える。感染者は回復しても、その後最長で2週間ウイルスを排出する可能性がある。 | ||||||
| 【ヘリコバクターピロリ】 | |||||||
| babA、cagA、dupA、iceA、oipA、vacA、virB、virC | 胃がんや胃潰瘍の原因の1つとされる一方で、特定のアトピー疾患、食道がんなどから宿主を守る働きも示唆されている。世界中の人口の約半数が有するといわれている。GI-MAPでは、8種類の遺伝子を調べる。これにより、抗生剤による3剤併用療法を行っても駆除できなかった場合に、次の治療を検討するうえでこの検査が有用となり得る。ピロリ菌は、その遺伝子の種類によって、リスクとなる疾患が異なり、たとえば、babAやCagAは胃がんと関連していたり、iceAはがんとは関連性はないものの消化不良や胃潰瘍などと関連していたりといったことがわかっている。急性感染では胃酸の分泌が低下し、慢性感染では臓器の部位によって分泌の低下や過剰が起こる場合がある。また、胃酸分泌の低下によって、SIBOが引き起こされることもある。ピロリ菌は細菌叢の多様性を低下させる可能性があるほか、ヒスタミンの放出を刺激(過敏性腸症候群、食物アレルギーの原因になり得る)するという報告もある。 | 〇 | 〇 | ||||
| 【共生/キーストーン細菌】 | |||||||
| バクテロイデスフラジリス Bacteroides fragilis |
人間の腸内に最初に定着する微生物の1つ。普段は無害であるが、高い腸管透過性、外傷、手術などによって血流に入ると重篤な感染症を引き起こすことがある。この細菌が多いと消化能力が低下したり便秘を起こしたりする可能性があり、少ないと腸内の抗炎症活性が低下する可能性がある。 | 〇 | |||||
| ビフィドバクテリウム属(ビフィズス菌) Bifidobacterium spp. |
腸内微生物叢に存在する有益な細菌の1つ。乳糖耐性の改善、下痢の予防、免疫システムの強化、食物アレルギーの軽減、悪玉菌の増殖抑制、腸内pHのコントロールなどの健康上の利点がある。この細菌が少ない場合、繊維の摂取が不足しているか、粘膜の状態が悪くなっている可能性がある。 ピロリ菌に対する阻害効果があるとされている。 |
||||||
| エンテロコッカス属(腸球菌) Enterococcus spp. |
腸球菌は、粘膜層下の腸上皮に沿って定着し、ここに定着することで腸の粘膜バリア機能を高める。また、バクテリオシンを産生して特定の菌による食中毒予防に重要な役割を果たしている。この細菌が多い場合、消化能力の低下、小腸腸内細菌叢の異常(SIBO)、無塩酸症(胃酸の欠乏)を反映している可能性がある。腸球菌は、粘膜に関連する微生物叢と考えられており、この細菌が少ないと粘膜や上皮の健康状態が低下している可能性がある。 | ||||||
| エシェリヒア属(大腸菌) Escherichia spp. |
経腟分娩中に母胎の糞便に曝露することで人間の腸に最初に定着する細菌の1つ。生後最初の数日で、バクテロイデス種やビフィズス菌種が定着して増殖できるよう嫌気性の環境を作る。ほとんどの菌株は非病原性であり、病原性大腸菌を阻害する働きがある。この値が高い場合、腸の炎症活動が高くなっている可能性があり、低い場合、粘膜の健康状態が低下しており、病原性大腸菌に対する防御能力が低下している可能性がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ラクトバチルス属(乳酸菌) Lactobacillus spp. |
プロバイオティクスに多く使用されている。この値が高い場合、消化能力の低下や炭水化物の過剰摂取の可能性があり、この値が低い場合、炭水化物の摂取が不足しているか、塩分の摂取が多い可能性があるほか、粘膜の健康状態が低下している可能性がある。ピロリ菌に対する阻害効果があるとされている。 | 〇 | |||||
| エンテロバクター属 Enterobacter spp. |
院内感染の原因菌として知られている。この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性があり、低い場合、粘膜の健康状態が低下している可能性がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| アッカーマンシアムシニフィラ Akkermansia muciniphila |
腸内に定着する善玉菌の1つで、クロストリジウム菌などの他の菌が酪酸などを産生するのをサポートする働きがある。この値が低いと、肥満、糖尿病、代謝機能障害、心血管障害のリスクが高まり、この値が高いと、多発性硬化症のリスクが高まる。ただし、日本人は他の人種・民族よりも保有率が低いとされる。 | ||||||
| フィーカリバクテリウム プラウスニッツイ Faecalibacterium prausnitzii |
腸内に定着する善玉菌の1つで、クロストリジウム菌などの他の菌が酪酸などを産生するのをサポートする働きがある。この値が低いと、肥満、糖尿病、代謝機能障害、心血管障害のリスクが高まり、この値が高いと、多発性硬化症のリスクが高まる。ただし、日本人は他の人種・民族よりも保有率が低いとされる。 | 〇 | |||||
| ローズブリア属 Roseburia spp. |
短鎖脂肪酸を生成し、エネルギー恒常性のバランスを維持する。結腸の運動性を促進し、免疫をサポートするほか、炎症の抑制機能もある。この値が低いと、過敏性腸症候群、肥満、2型糖尿病、アレルギー、心血管疾患のリスクが増加する。 | 〇 | |||||
| 【細菌門】 | |||||||
| バクテロイデス Bacteroidetes |
ファオーミキューテス門とともに、口、鼻、喉を含め、消化管全体に多く存在する優性細菌門。 | 〇 | |||||
| ファーミキューテス Firmicutes |
バクテロイデス門とともに、口、鼻、喉を含め、消化管全体に多く存在する優性細菌門。食物繊維の代謝、ビタミン等の合成、免疫系の維持、感染抑制などの働きがある。この菌が多いとメタン産生菌も多い可能性がある。 | 〇 | |||||
| ファーミキューテス/バクテロイデス比 Firmicutes:Bacteroidetes Ratio |
腸内のファーミキューテスとバクテロイデスの比率。高値、低値では細菌叢のバランスが崩れていることを示す。肥満者ではこの値が高く、減量するとこの値も低下するとの報告もあるが、これに異を唱える学者もいる。いずれにしても肥満者では細菌叢のバランスが崩れていることは明らかである。高脂肪食によってこの値も上昇する。細菌叢のバランスが崩れるのは肥満そのものが原因ではなく、食事によるものとする報告もある。この値が高い場合、低脂肪食、プロバイオティクス、プレバイオティクスによる治療が推奨される。グルタミン30グラムを2週間毎日摂取するとこの値が低下したとの研究もある。 | ||||||
| 【日和見菌/細菌の異常増殖】 | |||||||
| バチルス属 Bacillus spp. |
ファーミキューテス門に属するグループ。一部の菌株はプロバイオティクスに使用されている。この値が高い場合、消化機能の低下、SIBO、便秘などの可能性がある。 | ||||||
| エンテロコッカスフェカリス Enterococcus faecalis |
腸内に自然に存在する細菌の1つで、健康な人では無害であることが多い。最近、この菌の薬剤耐性菌が増えている。この値が高い場合、胃酸の減少、消化機能の低下、SIBO、便秘などが引き起こされる可能性がある。 | 〇 | |||||
| エンテロコッカスフェシウム Enterococcus faecium |
この菌の薬剤耐性菌が増えている。この値が高い場合、胃酸の減少、消化機能の低下、SIBO、便秘などが引き起こされる可能性がある。 | ||||||
| モルガネラ属 Morganella spp. |
この菌の薬剤耐性菌が増えている。この値が高い場合、胃酸の減少、消化機能の低下、SIBO、便秘などが引き起こされる可能性がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| シュードモナス属 Pseudomonas spp. |
自然界に広く存在し、牛乳、肉、魚介類、野菜などが汚染される可能性がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| シュードモナスエルギノーザ(緑膿菌) Pseudomonas aeruginosa |
感染症の原因菌として最も一般的な種の1つで、腸管の炎症、上皮バリアの機能不全、腸管透過性の増加を引き起こすことがある。ストレス、外傷、手術、がんなどによってその毒性が増強される。この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性があり、腹痛や軟便を引き起こすことがある。この菌の一部の株は、細胞にダメージを与える毒素を産生する。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ブドウ球菌属 Staphylococcus spp. |
グラム陽性の球菌で構成される菌属で、人や動物の粘膜や皮膚だけでなく、広く環境中に存在する。 | ||||||
| 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus |
ファーミキューテス門のグラム陽性菌。この値が高い場合、消化能力の低下や腸の炎症活動の可能性がある。また、一部の株は毒素を産生し、これが軟便や下痢を引き起こす。 | 〇 | |||||
| 連鎖球菌属 Streptococcus spp. |
ファーミキューテス門のグラム陽性菌。体内に広く存在し、通常は人体に問題はない。この値が高い場合、胃酸の低下、プロトンポンプ阻害剤の使用、消化能力の低下、SIBO、便秘などの可能性があるほか、腸の炎症活動が活発になっており、軟便の原因になり得る。 | 〇 | |||||
| デスルフォビブリオ属 Desulfovibrio spp. |
30種以上を含むグラム陰性菌属。細胞のシグナル伝達に影響を及ぼす。低値では酸化ストレスを軽減し、高値では毒性を有する硫化水素を産生する。高濃度の硫化水素は、結腸がん、潰瘍性大腸炎、結腸細胞への損傷との関連性がある。一方、硫化水素の濃度が正常であると、腸粘膜の健康に寄与することのほか、病原体の抑制、抗酸化能の促進をサポートする。このため、この値が低値であると、腸の健康に悪影響を与える可能性がある。デスルフォビブリオ種は、無症候性に消化管内に運ばれることもあれば、日和見病原体となることもある。また、細菌の異常増殖や潰瘍性大腸炎、クローン病などの炎症性腸疾患との関連性も示唆されている。 | 〇 | |||||
| メタノバクテリウム科 Methanobacteriaceae (family) |
メタンガスを産生する細菌様の微生物。共生細菌が炭水化物を発酵し、短鎖脂肪酸を生成するのをサポートしており、腸内の生態系で重要な役割を果たしている。この値が高い場合、慢性便秘、SIBO、IBSの可能性がある。特に、便秘型の過敏性腸症候群では、この科に属するメタノブレビバクタースミシーとメタンガスの増加が報告されている。メタンガスが過剰に産生されると、腸の蠕動運動が低下し、ガス溜まりや便秘の原因となり得る。 | 〇 | |||||
| シトロバクター属 Citrobacter spp. |
メタンガスを産生する細菌様の微生物。共生細菌が炭水化物を発酵し、短鎖脂肪酸を生成するのをサポートしており、腸内の生態系で重要な役割を果たしている。この値が高い場合、慢性便秘、SIBO、IBSの可能性がある。特に、便秘型の過敏性腸症候群では、この科に属するメタノブレビバクタースミシーとメタンガスの増加が報告されている。メタンガスが過剰に産生されると、腸の蠕動運動が低下し、ガス溜まりや便秘の原因となり得る。 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| シトロバクターフロインディー Citrobacter freundii |
この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性がある。 | 〇 | 〇 | ||||
| クレブシエラ属 Klebsiella spp. |
プロテアバクテリア門のグラム陰性菌。特に、尿中ヒスタミン値の高い過敏性腸症候群患者でクレブシエラアエロゲネスの量が多いことが確認されており、発酵性糖質食品の摂取を控えると尿中ヒスタミン値が低下したとの報告がある(ヒスタミンは過敏性腸症候群の症状を悪化させる)。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| クレブシエラニューモニエ(肺炎桿菌) Klebsiella pneumoniae |
口腔や気道によくみられる。下痢、ガス、腹痛、膨満感を引き起こすことがある。抗生物質の長期使用でリスクが高まる。腸内でヒスタミンを放出する可能性がある。この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| マイコバクテリウムアビウム亜種パラ結核 M.avium subsp. paratuberculosis |
放線菌門の細菌種。この値が高い場合、クローン病や関節リウマチとの関連性が示唆される。 | ||||||
| プロテウス属 Proteus spp. |
日和見感染症の原因病原体。消化管がこの菌属の貯蔵庫になり得、土壌や水中のプロテウス種を測定することで、その土壌や水がどの程度糞便に汚染されているかがわかる。この菌属に汚染された食品や水を摂取すると食中毒を引き起こすことがある。プロテウスはリポ多糖類を産生して炎症を増大させる可能性がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| プロテウスミラビリス Proteus mirabilis |
プロテオバクテリア門のグラム陰性菌。ヒトのプロテウス感染症で最もよくみられる原因菌。土壌、水域、施設、病院などの環境に広く存在。重篤な創傷感染では、全身性の炎症反応や敗血症を引き起こすことがある。ペットや野生動物が感染源となる場合もある。感受性の高い人に炎症性関節炎を引き起こすことがある。尿路感染の原因菌としてもよく知られている。この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性があるほか、軟便や下痢を引き起こす場合がある。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| エンテロバクター属 Enterobacter spp. |
プロテオバクテリア門のグラム陰性菌属。同じ分類科に属する大腸菌と密接に関連している。この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性があり、この値が低い場合、粘膜の健康状態が低下している可能性がある。 | 〇 | |||||
| エスケリキア属(大腸菌属) Escherichia spp. |
プロテオバクテリア門のグラム陰性菌属。正常な腸内細菌叢。ほとんどの大腸菌は非病原性(病原性大腸菌株についてはGI-MAPの「病原体」セクションで個別に測定)。この値が高い場合、腸の炎症活動が増加している可能性があり、この値が低い場合、粘膜の健康状態が低下しており、病原性大腸菌に対する防御能力が低下している可能性がある。 | 〇 | |||||
| フソバクテリウム属 Fusobacterium spp. |
フソバクテリア門のグラム陰性菌属。腸内や口腔内に存在する。全身性強皮症などの自己免疫疾患のほか、大腸がん、炎症性腸疾患、肥満、便秘型IBSなどさまざまな疾患とも関連があるとされている。 | 〇 | 〇 | ||||
| プレボテラ属 Prevotella spp. |
バクテロイデス門のグラム陰性菌属。関節リウマチと関連している。ヒトの腸内に自然に存在する細菌群で、炭水化物や繊維質を分解する。一部のプレボテラ属の菌は炎症性疾患と関連している。この値が高い場合、消化能力の低下やでんぷんの多い食事が過剰である可能性がある。 | ||||||
| 【真菌/酵母】 | |||||||
| カンジダ属 Candida spp. |
消化管や皮膚粘膜に自然に存在する酵母の一種。正常な便検体の40~80%で検出される。ただし、この値が高くなり過ぎたり、他の有益な菌群とのバランスが崩れたりすると、さまざまな症状を発症するようになる。 | 〇 | |||||
| カンジダアルビカンス Candida albicans |
皮膚、口、消化管に存在する酵母菌の一種。カンジダが異常に増殖して起こる真菌性腸内毒素症やカンジダ過敏症は、原因がまだ明確になっていないが、胃腸の不調、疲労、倦怠感、皮膚の発疹、頻尿、筋肉痛、関節痛、下痢、便秘などを引き起こす。 | 〇 | |||||
| ゲオトリクム属 Candida albicans |
腸内に存在する環境菌の一種。免疫抑制状態の人や火傷などの外傷を負った人に最も多く病気を引き起こす可能性がある。下痢、腸炎、クローン病、過敏性腸症候群などの胃腸疾患や、全身の健康状態、栄養吸収と関連がある。一部の菌株はソフトチーズの生産に使用される。この値が低い場合、食事による一時的な影響が考えられる。 | ||||||
| ミクロスポリジウム(微胞子虫) Microsporidium spp. |
当初はカイコの寄生虫とされていたが、現在は真菌とされている。GI-MAPでは、胃腸に影響を与える微胞子虫「エンセファリトゾーン・インテスティナリス」を検出する。HIV患者、臓器移植を受けた患者、化学療法を受けている患者など、免疫が抑制されている人でよく感染するが、健康な人にも感染することがあり、その場合、下痢がよくみられる。 | ||||||
| ロドトルラ属 Rhodotorula spp. |
土壌、植物、浴室、液体(牛乳、水等)など、広く環境に存在する菌類。ほとんどのヒトに存在する常在菌と考えられている。免疫抑制患者では病気を引き起こす可能性がある。 | ||||||
| 【ウイルス】 | |||||||
| サイトメガロウイルス(CMV) Cytomegalovirus |
サイトメガロウイルス(CMV)は、日本人の多くが母子感染を介して保有するヘルペスウイルス。普段は体内に潜伏して症状がないものの、免疫力が低下または抑制されている場合に再活性化して、発熱、脳炎、大腸炎など、さまざまな症状が出てくることがある。GI-MAPでこのウイルスが陽性の場合、過去の感染ではなく、現在消化管で活動中の感染であることを示す。陽性でも症状がみられない場合は、特に治療は必要ない。糞便検査によるCMV値は、血漿CMV値と相関していることからCMVによる胃腸疾患の指標となり得る。炎症性腸疾患(IBD)患者でCMV DNAのレベルが高いことがわかっている。IBDの病態生理において、これまで考えられていた以上にCMVが影響していることが示唆される。IBD患者のCMV感染率は10~36%との報告もある。 | ||||||
| エプスタインバーウイルス(EBV) Epstein-Barr Virus |
伝染性単核球症を引き起こすことがあるヘルペスウイルス。全身性エリテマトーデス、全身性硬化症、1型糖尿病、関節リウマチなどの自己免疫疾患の発症に関与していると考えられている。狼瘡や全身性硬化症といった一部の自己免疫疾患では、健康な人よりもCMVに対する抗体がはるかに高いことがわかっている。GI-MAPでこのウイルスが陽性の場合、過去の感染ではなく、現在消化管で活動中の感染であることを示す。EBVウイルスは上皮細胞に侵入するため、特にピロリ菌にも同時感染している場合、胃がんのリスクを高める可能性がある。IBD患者のEBV感染率は30~64%。IBD患者では、このウイルス量が多いほど、腸管粘膜の損傷度合いが高いことが確認されている。 | ||||||
| 【寄生虫】 | |||||||
| ブラストシスチスホミニス Blastocystis hominis |
ヒトや動物の腸内に生息する単細胞生物。症状の有無を問わず世界中の人にみられる。ブラストシスチス感染症の主な症状は、下痢、水様便、腹痛、肛門のかゆみ、便秘、ガスの過剰産生、皮膚疾患などがある。過敏性腸症候群などの慢性消化器疾患との関連性が疑われている。 | ||||||
| キロマスティックスメスニリ(メニール鞭毛虫) Chilomastix mesnili |
消化管に生息する単細胞生物。基本的に非病原性であるが、下痢に関する症例の報告もある。 | ||||||
| サイクロスポラ属 Cyclospora spp. |
サイクロスポラ症という腸の感染症を引き起こす寄生虫群。特に熱帯、亜熱帯地域の汚染された水や食品を介して感染し、下痢、腹痛、食欲不振、体重減少、嘔吐などの症状を引き起こすほか、頭痛や微熱など、インフルエンザのような症状を引き起こすこともある。通常は、7日程度で軽快する。 | ||||||
| ディエントアメーバフラジリス(二核アメーバ) Dientamoeba fragilis |
ヒトやブタの消化管に生息する単細胞生物。旅行者下痢症でよくみられる。無症状のこともあれば、基準値を超えない中程度の量でも、下痢、腹痛、発熱などの症状を引き起こすことがある。 | ||||||
| エンドリマックスナナ(小形アメーバ) Endolimax nana |
消化管によくみられる単細胞生物。汚染された食品や水を介して感染する。非病原性であると考えられ、無症状であることが多い。 | ||||||
| 大腸アメーバ Entamoeba coli |
大腸に生息するアメーバで、病原性はないとされている。ただし、検査で存在が確認された場合、他の病原性微生物がいる可能性がある。 | ||||||
| ペンタトリコモナスホミニス(腸トリコモナス) Pentatrichomonas hominis |
汚染された水や食品を介して感染する寄生虫。基本的に病原性はないとされているが、小腸がんの患者に多くみられるとの論文もある。症状が出ることはほとんどないが、腸内細菌叢に異常を来すこともある。犬や猫にも感染する。 | ||||||
| ズビニ鉤虫 Ancylostoma duodenale |
ヒトに感染する腸の鉤虫の一種で、皮膚に侵入して鉤虫感染症を引き起こす。体長10~12mm。感染幼虫が付いた食品を摂取すると、主に小腸で成虫となり、1~1.5年間生存する。感染幼虫の一部は腸管を経由して肺に達する。初期症状は幼虫が侵入した皮膚のかゆみと発疹、重篤になると腹痛、下痢、疲労、体重減少、貧血、食欲不振などを起こす。鉤虫感染は、子どもの身体的および認知的成長に影響を及ぼす可能性がある。また、宿主の血液を持続的に吸い取ることから、小児や妊娠中の女性に鉄欠乏性貧血を引き起こすことがある。犬や猫の小腸にも生息するためペットも暴露源となり得る。 | ||||||
| ヒト回虫 Ascaris lumbricoides |
ヒトに最もよくみられる腸の寄生虫。汚染された水や食品を介して感染する。無症状の場合や肺症状、重度の消化器症状を起こすことがある。感染初期には発熱、咳、喘息、呼吸困難などがみられ、後期には腹痛、悪心、嘔吐、頻回な咳、のどのちくちく感、膵炎などがみられる。初期段階では、血液中の好酸球数が高くなることがあるが、便中の寄生虫卵や寄生虫検査は陰性であることが多い。 | ||||||
| アメリカ鉤虫 Necator americanus |
ヒトに感染する腸の鉤虫の一種で、皮膚に侵入して鉤虫感染症を引き起こす。体長10~12mm。感染幼虫が皮膚から侵入すると、血流にのって肺に達し、肺胞から気管、咽頭、胃を経由して小腸に達して成虫となる。初期症状は幼虫が侵入した皮膚のかゆみと発疹、重篤になると腹痛、下痢、疲労、体重減少、貧血、食欲不振などを起こす。鉤虫感染は、子どもの身体的および認知的成長に影響を及ぼす可能性がある。また、宿主の血液を持続的に吸い取ることから、小児や妊娠中の女性に鉄欠乏性貧血を引き起こすことがある。犬や猫の小腸にも生息するためペットも暴露源となり得る。 | ||||||
| トリキュリストリキウラ(鞭虫) Trichuris trichiura |
土壌を介して、またはヒトからヒトへに感染する回虫で鞭虫症を引き起こすことがある。主に衛生環境が悪い地域で蔓延する。感染すると無症状の場合もあれば、下痢や血便を起こすこともある。貧血を起こしている場合、鉄のサプリメントが有用な場合もある。 | ||||||
| テニア属(サナダムシ) Taenia spp. |
ヒトや動物に感染を引き起こす条虫。汚染された加熱不十分な豚肉(有鉤条虫)や牛肉(無鉤条虫)を摂取した後に便中に見つかることがある。1匹の条虫でも感染を引き起こす。感染しても無症状であるか症状があっても軽症であることが多い。症状は、腹痛、吐き気、脱力感、食欲亢進、食欲不振、頭痛、便秘、めまい、下痢、肛門のかゆみ、貧血などがある。PCR法が感度が高く、便中の有鉤条虫種を高感度に特異的に検出できる。 | ||||||
| 【腸の健康マーカー】 | |||||||
| ステアトクリット Steatocrit |
膵臓不全や小腸吸収不良患者の脂肪便を検出するために広く使用されている検査法で、便中の脂肪量を測定する。通常、脂肪は胆汁酸で乳化された後、小腸で吸収される。1日の糞便中には約2~6gの脂肪が含まれるとされており、便中の脂肪量が多い場合、消化不良や吸収不良の可能性がある。この値が高い場合、低塩酸症、消化不良、吸収不良、膵臓機能不全、胆汁酸塩の欠乏、不十分な咀嚼、セリアック病などが考えられる。 | ||||||
| エラスターゼ-1 Elastase-1 |
タンパクを分解する酵素の1つで、膵臓のみから分泌され、膵臓の機能を直接反映する。膵臓の機能がうまく働かなくなり、炎症を起こすと膵臓機能不全となる。膵臓機能不全になると、脂溶性ビタミンなどの栄養素を吸収しにくくなるため、脂肪便、腹痛、吸収不良などの症状を示す。低値の原因として、膵臓機能の低下、胆石、ピロリ菌が存在する場合の低塩酸症、嚢胞性線維腺症が挙げられるほか、SIBOでもみられる場合がある。また、ベジタリアンで値が低いことがある。100μg/g未満の場合、重度の膵外分泌機能不全が疑われる。 | ||||||
| βグルクロニダーゼ β-Glucuronidase |
肝臓、腎臓、腸上皮、内分泌、生殖器官の細胞や腸内の一部の細菌によって生成される酵素で、化学物質や毒素の分解に関係している。この酵素が血漿中で上昇すると、乳がんや前立腺がんなどのホルモンに敏感ながんのリスクが増加する。この値が高い場合、SIBO、大腸がんリスクの増加、解毒不良、毒素または薬物への過剰曝露などが考えられる。ベジタリアンではこの値が低く出ることがある。 | ||||||
| 免疫学的便潜血(FIT) Occult Blood - FIT |
大腸がんのスクリーニング検査法で、便中のヘモグロビンの量を測定する。陽性の場合、出血性潰瘍、炎症性腸疾患、がん、腸ポリープ、上部消化管出血などが考えられる。 | ||||||
| 分泌型IgA Secretory IgA |
異物が侵入したときにそれを攻撃するため消化器系に分泌される抗体タンパク質(免疫グロブリン)。病原性の微生物に対する最初の免疫防御として働く。この免疫グロブリンは、腸内微生物叢に影響を与え、腸のバリア機能を維持するために、腸内病原体やアレルゲンと複合体を形成し、それらが腸管障壁を透過するのを防ぐ。分泌型IgAの機能が低下すると、腸の感染症、アレルギー性疾患、炎症性疾患のリスクが増加する可能性がある。慢性的なストレスも分泌型IgAのレベルを乱すことがある。高値は、慢性感染や炎症反応に対して活性化された免疫応答を示している可能性がある。低値の場合、腸管免疫機能が低下している、慢性的にストレスを受けている、免疫力が低下している、タンパク質不足の栄養失調などが考えられる。 | ||||||
| 抗グリアジンIgA Anti-gliadin IgA |
グリアジンは、小麦や大麦、麦芽、ライ麦などの穀物に含まれるタンパク質「グルテン」の成分。糞便中に抗グリアジン抗体が存在するということは、食事で摂ったグルテンに対して腸内で免疫反応を示している可能性がある。グリアジンは腸の免疫を刺激するため抗グリアジン抗体が血清で検出できるようになるかなり前に糞便中で検出される。セリアック病の診断にも用いられる。高値の場合、グルテンフリー食への切り替えを検討する。また、腸管バリアのサポート(亜鉛カルノシンやLグルタミンのサプリメント)も考える。 | ||||||
| 好酸球活性化タンパク質(EDN、EPX) Eosinophil Activation Protein(EDN、EPX) |
感染症(特にウイルス感染症)やアレルギー反応、炎症反応時に、腸管腔内で活性化された好酸球によって放出されるタンパク質で、便中で検出される。強力な細胞毒性を持ち、さまざまな炎症性疾患やマスト細胞が関わる病態で重要な役割を果たす。腸内でこのタンパク質が蓄積している場合、炎症や組織損傷が疑われる。便中のこのタンパク質の量は、消化管の慢性炎症の客観的な尺度となり得る。高値の場合、呼吸器アレルギー、喘息、食物アレルギー/過敏症、IBD、IBS、好酸球性食道炎、機能性ディスペプシア、胃酸の逆流、腸管バリアの損傷/機能不全、腸内寄生虫などが考えられる。 | ||||||
| カルプロテクチン Calprotectin |
炎症に反応して白血球から放出されるカルシウム結合タンパク質で、好中球に高濃度で存在する。また、単球、マクロファージ、腸上皮細胞にもみられる。炎症性腸疾患(IBD)の診断とモニタリングの標準的なマーカーとされているほか、IBDと過敏性腸症候群を区別するのにも用いられる。IBDの診断には有用なマーカーであることは広く認められているが、IBDの基準値については、50μg/gとする検査や100μg/gとする市販の検査、あるいは400~1000μg/gとする研究など、統一見解は得られていない。しかし、600μg/gを超えるとIBDと強く相関する。このほか、非ステロイド性抗炎症薬の過剰摂取による腸疾患で値が高くなることがあるため、非ステロイド性抗炎症薬を一時中止してから検査する方がよい場合もある。高値の場合、腸の感染症、炎症促進性腸内細菌叢の異常、食物アレルゲン、毒素、非ステロイド性抗炎症薬の使用、炎症性腸疾患、ポリープ、憩室炎、結腸直腸がんなどが考えられる。 | ||||||
| 【オプション検査】 | |||||||
| ゾヌリン Zonulin |
腸の粘膜バリアを調節するタンパク質。消化管の粘膜には細胞間をつなぐ「タイトジャンクション」というバリア機能が形成されており、腸を通る食べかすや毒素、細菌等が組織に侵入するのを防いでいる。ゾヌリンは、このタイトジャンクションを開く働きがある。いわゆるこの水門が開いてしまうと、食べかすや毒素、細菌等が組織、血流に侵入し、免疫機能不全や食物アレルギー、過敏性腸症候群、自己免疫疾患などの原因となる「リーキーガット」を引き起こす。高値の場合、グルテンフリー食への切り替えや食物過敏症に対応する。Lグルタミン酸、亜鉛カルノシン、プロバイオティクス等のサプリメントで腸バリアをサポートする。 | ||||||
| グルテンペプチド Gluten Peptide |
便中のグルテンの量。検査前2~4日間のグルテンの摂取を反映する。グルテンフリーの食事を心がけているか、意図せずグルテンが含まれる食事を摂っていないかを確認できる。 | ||||||
| 総合抗生物質耐性遺伝子パネル Universal Antibiotic Resistance Gene Panel |
10種類の抗生物質クラスについて55の遺伝子の有無を調べる。これにより、ある病原菌の治療のため抗生剤を使用するにあたり、どの種類の抗生剤が効かないか、あるいは効きづらいかを事前に把握でき、その抗生剤を避けることで、遠回りせず、効率的および効果的な治療が期待できる。入院歴のある人、抗生剤による治療歴のある人、頑固な慢性感染症がある人に有用。 | ||||||
| StoolOMX | 便中の25種類の胆汁酸と9種類の短鎖脂肪酸の量を調べる検査。これにより、胆汁性下痢症、腸管運動能、胆汁酸不足による便秘等に関する情報が得られる。詳細はこちら。 | ||||||
※1 マスト細胞を活性化する細菌。マスト細胞の活性化は、過敏性腸症候群や食物アレルギーなどの原因となることがある。
※2 ヒスタミン産生菌。ヒスタミンが過度に産生されると、マスト細胞が活性化されて過敏性腸症候群などを引き起こすほか、食物アレルギーの原因にもなり得る。
※3 LPS(リポ多糖)産生菌。LPSが過剰になるとマスト細胞が活性化され、過敏性腸症候群や食物アレルギーなどの原因となることがある。
※4 水素産生菌。水素には抗酸化作用がある一方で、これをエサにして増える硫酸還元菌は、たとえば便秘型過敏性腸症候群を引き起こすことがある。
※5 メタン産生菌。メタン産生菌が多いと、腸管の運動が低下して食物の大腸通過時間が長くなり、慢性便秘を引き起こすことがある。
※6 硫化水素産生菌。硫化水素は、腸管の運動能や内臓の神経過敏に影響する可能性が示唆されている。また、硫化水素のが過剰に産生されるとおならが臭くなる。
GI-MAP検査の費用
| 診療メニュー | 料金(税込み) |
|---|---|
| GI-MAP検査 | 90,000円~110,000円 (その時期の為替レートによる) |
| 初診料 | 11,000円(25分) |
| 再診料(結果説明) | 8,800円(20分) |
※必ず電話で予約をおとりください。
※自費診療枠:月・火・金・土の14:00~15:00(祝日を除く)
